Column: オタワ便り NO.36 (2025年4月)
オタワ便り第36回4月 日加科学技術協力〜オタワ大学と福井大学の医学研究協力
山野内在カナダ大使
日加協会の皆様、日加関係を応援頂いている皆様、こんにちは。
はじめに
4月の声を聞き、オタワにも早春の雰囲気が漂って参りました。一方、カナダは非常に熱い政治の季節に突入しています。
約10年に及んだトルドー首相が退陣し、3月14日(金)カナダ銀行総裁・イングランド銀行総裁を歴任したマーク・カーニー氏が新首相に就任しました。カーニー首相は、3月23日(日)には議会を解散。4月28日(月)に総選挙が行われます。自由党が政権を維持するのか、ピエール・ポリエーブ党首率いる保守党が10年振りに政権を握るのか注目されます。最大の焦点は、25%関税と51番目の州を主張するトランプ政権に対し、どちらがより良くカナダの国益を守れるのかです。3月末の時点では、世論調査は自由党有利です。一方、トランプ政権の動向も含め国際情勢も内政面でも様々な出来事が起こっており、選挙に陰に陽に影響を与えます。1ヶ月の選挙運動期間で何があってもおかしくありません。カナダの総選挙については次回の「オタワ便り」で詳しく報告させて頂きます。
このような政治状況にあって、私としては、カナダ政府関係者、連邦議員、有識者等との接触を通じて現状の理解に努めているところですが、同時に日加関係の全般的な発展に資するよう、政治に限らず様々な分野の方々との面談やイベントに参加している次第です。特に、科学技術分野での協力には実に大きなポテンシャルがあると確信しています。
最近もオタワ大学の学長、副学長等を公邸にお招きする等、大学・研究機関との交流を強化しています。示唆に富む話も多く伺います。そんな中で、オタワ大学と福井大学の医学部の間で25年に及ぶ共同研究が続いていることを知りました。また、オタワ大学で国際共同研究を推進するためのパネル・ディスカッションでの基調講演についても依頼されました。
と言う訳で、今月の「オタワ便り」は、オタワ大学を軸にした科学技術協力についてです。
科学技術と外交
まず、科学技術協力の背景について概観したいと思います。
目を太古の時代に向けます。人類の歴史を振り返ると、二本足歩行を始めた瞬間から、自由になった手で道具を使い始めました。火を制御し、石器をつくり、木を加工し、人間の何倍も大きく強いマンモスら野生の動物に対峙し、生き延びて来ました。やがて高度な技術力を獲得し、土器から銅や鉄といった金属を加工するようになります。
時代が下り、印刷機、蒸気機関等、現在に直結する科学技術を獲得。20世紀には、人間が空を飛び、宇宙へ到達、原子力も利用し始めました。利便性も向上しましたが、一度戦争に使用されれば壊滅的な破壊力をも持ち得ます。科学技術には光と影があるのです。21世紀になり人工知能を獲得しています。科学技術が社会のあり方を規定し、安全保障に直結し、新しいビジネスを生み出し、未来をデザインしています。国力の礎です。圧倒的な科学技術の進歩は、G7広島サミットでAIが中心的な議題となったように、外交の世界においても極めて重要な課題となっています。この「オタワ便り」でも累次に亘りハイテク、科学技術等について累次報告しています。
今日の科学技術の進化は、日進月歩というか秒進分歩とも言うべき状況を呈しています。この関連で、本年2月、実に興味深い国際会議がボストンで開催されました。米国科学振興協会(AAAS)の年次総会です。ここで、AAASと英国王立協会(Royal Society)により作成された「分断の時代の科学技術外交」と題する報告書が発表されたのです。論点は3つです。第1に、科学外交は国際関係を推進する重要なツールであり、第2に、科学外交は非国家主体によってますます活用されており、第3に、混乱の時代には科学外交が求められる、というものです。
正に、日本として、米国を筆頭に同志国との間で科学技術分野での協力を一層強化する必要がありますが、カナダとの科学技術協力も大きな進展を見せています。
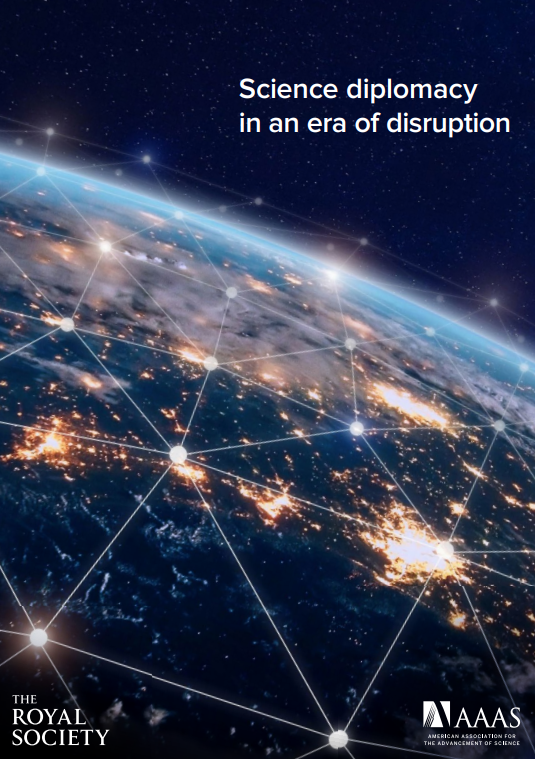
Science diplomacy in an era of disruption
写真出展: AAASのHP
オタワ大学における科学技術外交セミナー
そんな中、2月24日(月)、オタワ大学において、日加間の科学技術協力の推進に関するパネル・ディスカッションが開催されました。フレモント学長、サン・ピエール副学長はじめオタワ大学の教授陣、モナ・ネマ首席科学顧問、シャルボネ加イノベーション基金理事長等の錚々たる関係者も参加されました。日本からは福井大学医学部吉田教授らが来訪されました。
私は基調講演を依頼され、概要以下の諸点について述べました。
① 2025年2月現在、世界を見渡せば、状況は非常に複雑であり不透明感が漂う不確実な時代に生きていると実感する。そんな中、今日の国際情勢を特徴づける要素を3つあげれば、(i)地政学、(ii)地球温暖化、(iii)ハイテクだ。この3点は相互に作用し合っているが、最先端の科学技術が鍵である。故に、科学技術協力は今日の外交の主要テーマだ。が、重要なことは、国家安全保障にも直結し得る科学技術協力は真に信頼できる国との間でしか深化できないということだ。
② そこで、日本からすれば、G7であり基本的価値も共有するカナダとの科学技術協力は極めて重要だ。カナダは、インスリンを世界で初めて発見し、人工衛星を米ソに次いで開発・運用、世界初の商業ベースのCCS(二酸化炭素回収・貯留)を建設・運用し、AIのゴッドファーザーを生み、世界初の量子コンピューターを商品化した国だ。世界最先端の技術力を誇る。
③ 日加間では実に多彩で多様な科学技術協力が進行中である。例えば、京大・マギル大のゲノム分野でのジョイントPh.Dプログラム、NRC初の海外事務所が東京に設立、国立研究開発法人JSTとNRCの共同プロジェクト、AI・量子・クリーン技術・半導体・ライフサイエンス等の産業技術に関する日加協力覚書。
④ 今後の日加協力において重要なポイントは、(i)日加だけではなく、米欧の同志国との多層的な連携、(ii)科学技術をビジネスに結びつけるイノベーション、(iii)研究セキュリティーである。
⑤ 日加協力は大きな潜在力を持つが、カナダ側に望みたいのは、研究開発費の一層の増額だ。カナダの対GDP比は僅か1.7%で世界23位。因みに、米は3.6%で4位、日本は3.4%で5位。
⑥ 最後に、真の協力は信頼と尊敬とヴィジョンを共有する研究者の情熱から発展するものだと確信する。一つの素晴らしい実例が、25年に及ぶオタワ大学と福井大学の医学部産科婦人科間の協力だ。大きな成果が生まれつつある。

オタワ大学で講演する山野内大使
写真出展: オタワ大学HP
オタワ大学と福井大学との協力〜継続は力なり
そこで、オタワ大学と福井大学の医学部間の国際協力についてです。始まりは、2000年3月に遡ります。両大学の医学部間で学術交流パートナーシップが結ばれたのを受けて、ベンジャミン・ツァン教授と吉田好雄教授との産婦人科分野での共同研究が始まりました。
ツァン教授は、ミネソタ州ベミジー州立大学卒業後、アイオア大学で生命化学修士号、更にオタワ大学で博士号を取得。1980年からオタワ大学で研究され、オタワ地区癌財団のエンジェル賞はじめ多数の賞を受賞されています。国際的に著名な卵巣生物学者で女性の不妊症や卵巣癌等の健康問題に取り組んでおられます。
吉田教授は、前身の福井医科大学から一貫して、福井大学で婦人科腫疾患について研究を進めておられます。世界で初めて画像と血液による新たな子宮肉腫の診断法を開発された人物です。この功績で福井県がミニ・ノーベル賞と位置付ける「県科学学術大賞」を受賞されています。また、子宮肉腫の肺への転移メカニズムも明らかにされています。
長年に亘るツァン教授、吉田教授の国際共同研究は、婦人科腫瘍学や生殖医学等に関し大きな成果を生み、国際的にも高く評価されています。また、両大学の教授・研究者・学生の相互交流も両教授のリーダーシップで大きく発展させて来ました。2020年11月には、新型コロナ感染爆発で、国際的な交流が制約される中ながら、オタワ大学医学部と福井大学医学部との間の部局間学術交流協定が締結されました。この協定は、それまで産婦人科間の協力から医学部間の協力・交流へと発展したことを意味します。そして、吉田教授は「今後は大学間の包括協定に拡大していきたい」と抱負を語っておられます。
そして、現在はオタワ大学医学部のツァン教授の研究室にポスドクフェローとして、福井大学医学部より井上大輔博士が派遣され、最先端の研究に従事されています。近年は、オンラインで様々なコミュニケーションも可能であるが故に、オンラインの共同研究も少なくないですが、実際に研究者が現場を共有することは非常に重要です。

福井大学とオタワ大学の意見交換の様子
写真ご提供: 福井大学よりご提供
婦人科がん診断最前線
そして、2025年2月には、福井大学から4名の教授陣がオタワを訪問されました。これまで共同研究を基礎に、更に次の次元への飛躍に繋がる重要な訪問だと伺いました。その象徴が遠赤外領域開発センターの谷正彦教授です。医学部産婦人科の共同研究に、工学部の谷教授が参加されたところに、大きな意味があると言うのです。非常に高度で難解な事を文系の私なりに簡略に記します。
谷教授は、電磁波のひとつテラヘルツ波(遠赤外光)を研究されています。テラヘルツ波は、宇宙創生のビッグバンの名残りである宇宙背景放射でもあります。現代物理の基礎となっている量子力学は、物理学者プランクがテラヘルツ波の実験データをもとに導き出した放射式が出発点です。そして、テラヘルツ波は、光の直進性と電波の特性を兼ね備え、物質に対し高い透過性を持っています。と言うことは、X線のように高エネルギーの電磁波ではないので、物資や人体を痛めることなく透過し、表に見えないものを見ることができるのです。そのため、産業製品の非破壊検査や空港等の保安検査分野への応用が期待されています。そして、今医療分野への応用も視野に入って来ました。
今回、医学部の吉田教授が目をつけたのは、婦人科がんの検査・診断に・治療にテラヘルツ波を活用するというアイデアです。谷教授にお話を伺うと、最初に今回のオタワ大学訪問チームへの参加を打診された時は半信半疑だったそうですが、一連の会合を経て、世界を変え得る大きな可能性を確信するに至ったそうです。
現在、婦人科がんの検査・診断には、大型のCTやMRIスキャナーが必要です。が、テラヘルツ波を活用したセンサーが開発されれば、携帯電話ほどの大きさの機器で簡単に検査できるようになるのも夢ではなくなると言います。身体の中でも最もデリケートな子宮や卵巣に負担を与えることなく検査・診断が出来れば、世界中の女性にとっての朗報となります。正に、世界最先端の研究開発です。
この関連で、今回の福井大学ミッションに参加された定清直教授にも触れさせて頂きます。定教授はゲノム科学・微生物学の専門でらっしゃいますが、同時に2016年以来、学長補佐を務められています。最大の使命は、大学内の異なる学問領域のクロスオーバーだそうです。正に、婦人科がん診断にテラヘルツ波を活用するという発想を実際の開発プロジェクトへと昇華させていく推進力となっておられます。
結語
上述のとおり、25年に及ぶオタワ大学と福井大学の共同研究が大きな成果を生み出しています。同時に、両大学は、共同研究を創始しこれまで牽引して来たツァン教授、吉田教授の後継者も育てています。ソニー・シン教授と折坂誠准教授です。松明は確実に次の世代に引き継がれています。

これまでの共同研究への貢献に対し福井大学より名誉博士号を授与されるツァン教授
写真出展: 福井大学
ここで、福井大学医学部にまつわるエピソードを一つ。本年1月に、松阪桃李が主演した、小泉嶤史監督の映画『雪の花―ともに在りてー』が公開されました。江戸時代末期の福井藩で大流行した天然痘と闘った医師・笠原良策の半生を描いた吉村昭の同名小説が原作です。笠原は、欧州で効果をあげた種痘を導入しようとしますが、鎖国の日本では種痘に反発する庶民の妄信と藩の無理解で頓挫します。生涯をかけてこれと闘い抜き、幕府をも動かし、最終的に種痘で人々を天然痘から救った笠原の実話に基づいています。笠原は後年、敬意を込めて「笠原白翁」と呼ばれました。ここから福井大学医学部の同窓会は「白翁会」と称しているそうです。そんな笠原のDNAがオタワ大学と福井大学の共同研究にも宿っているようです。
そして、最後に、在カナダ日本大使館の科学技術アタッシェ、文科省出身の田村泰嗣書記官が作成した「科学技術・イノベーション動向報告・カナダ編」を参考までに。
ここには、カナダにおける科学技術に関する最新情報が包括的にまとめられています。カナダの全ての州に足を運び、関係者と面談した素晴らしい労作です。新たな日加科学技術協力のエンブリオです。ここから、次の世代を制する共同開発が生まれることを期待しています。
(了)
文中のリンクは日加協会においてはったものです。
Ontario/オンタリオ州
- オンタリオ州について
Ottawa/オタワ
- オタワについて

